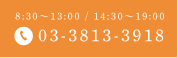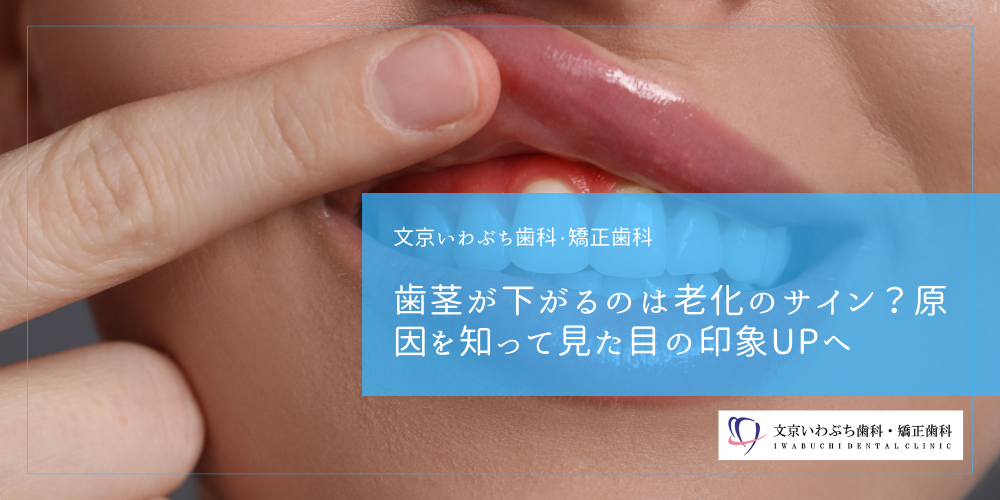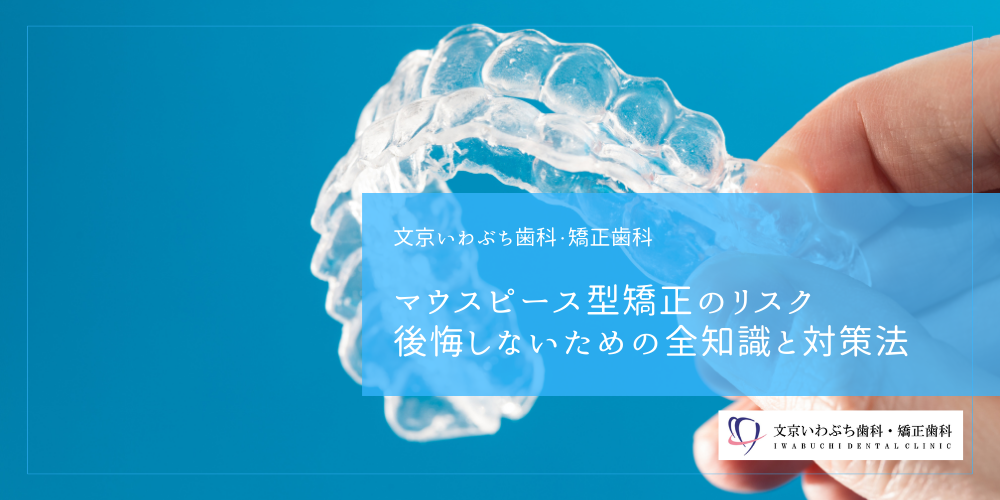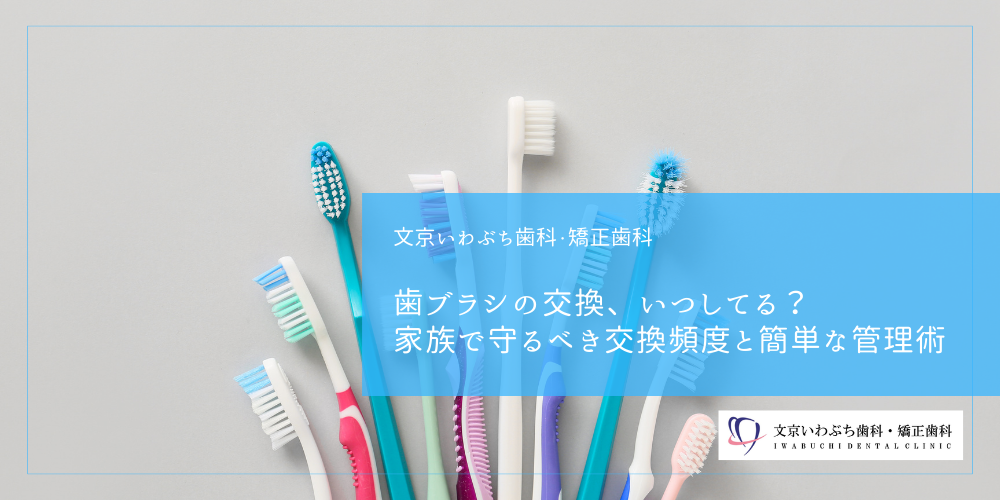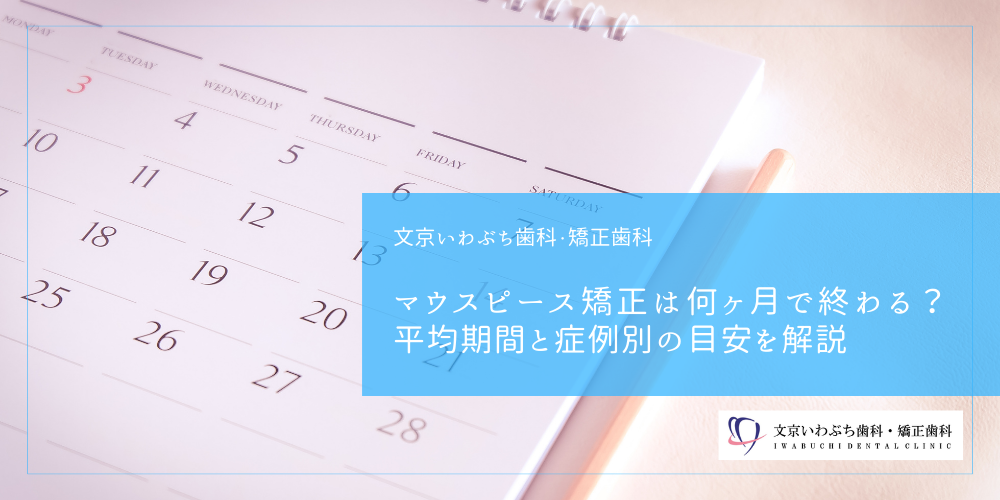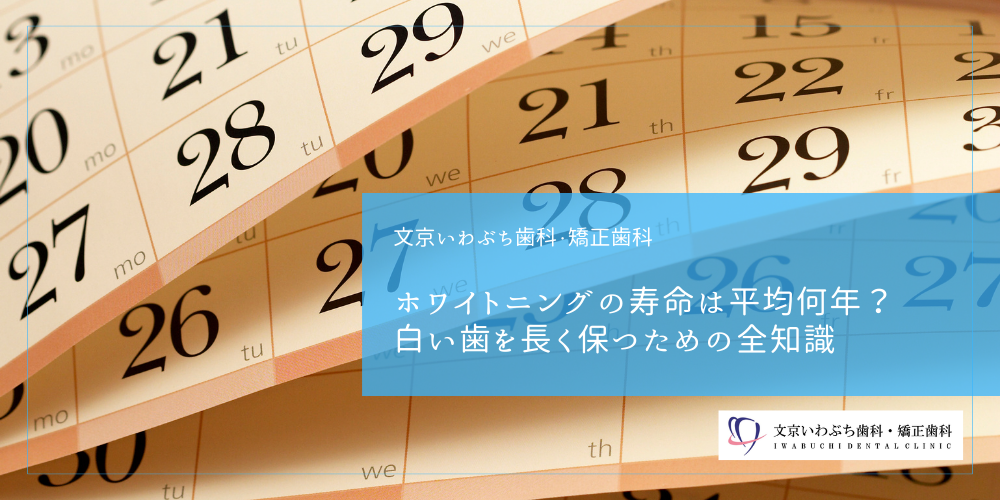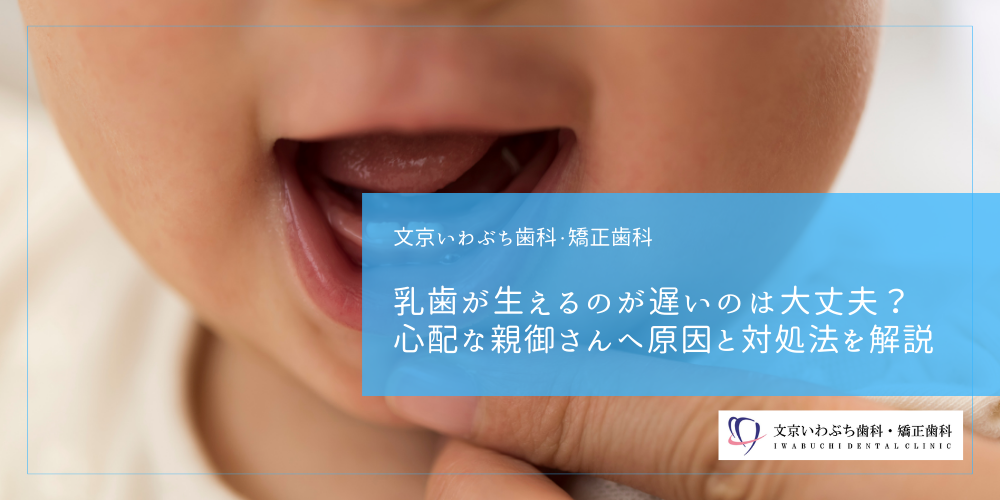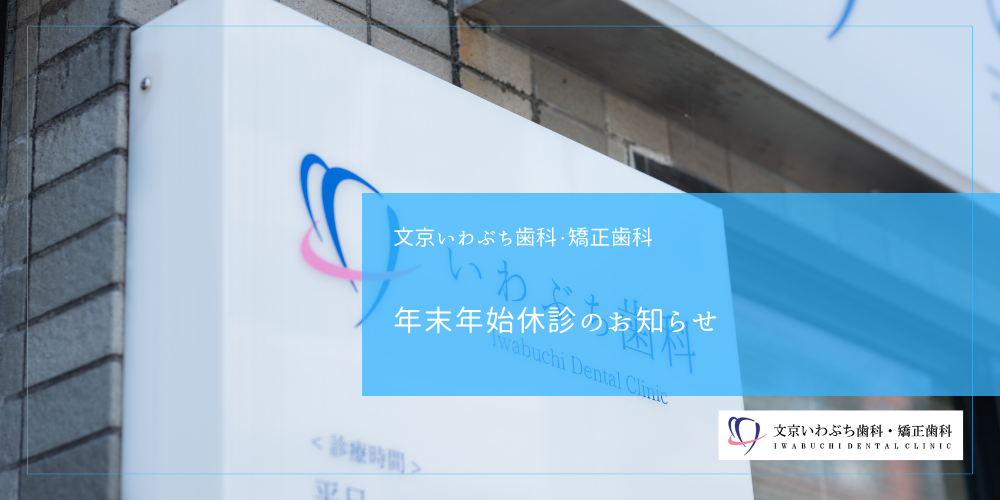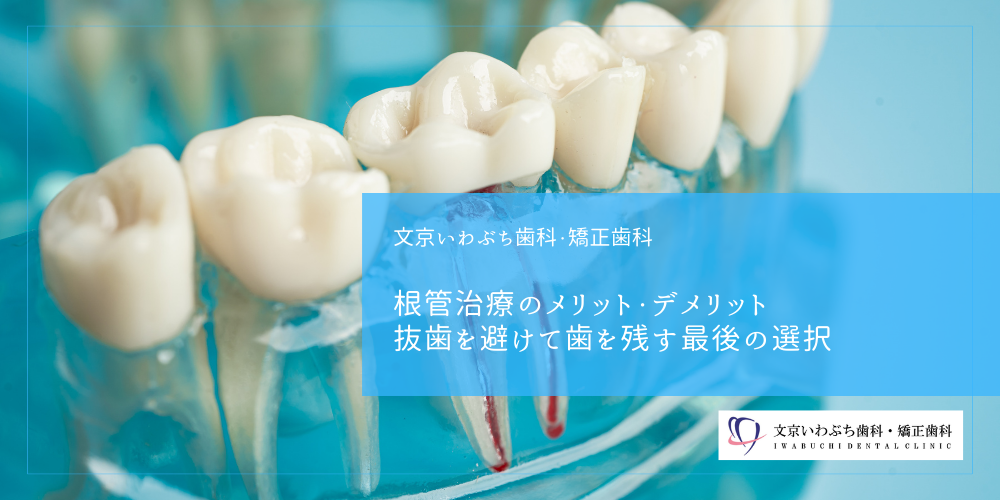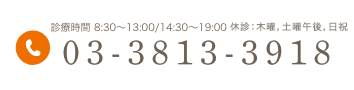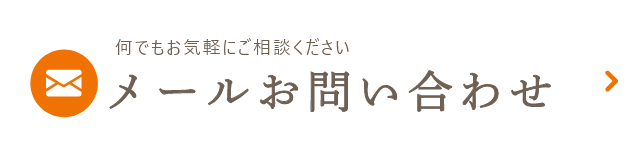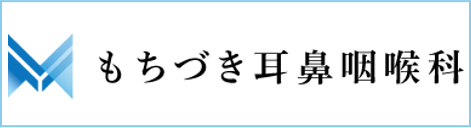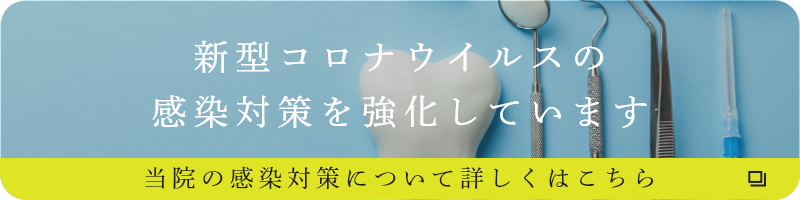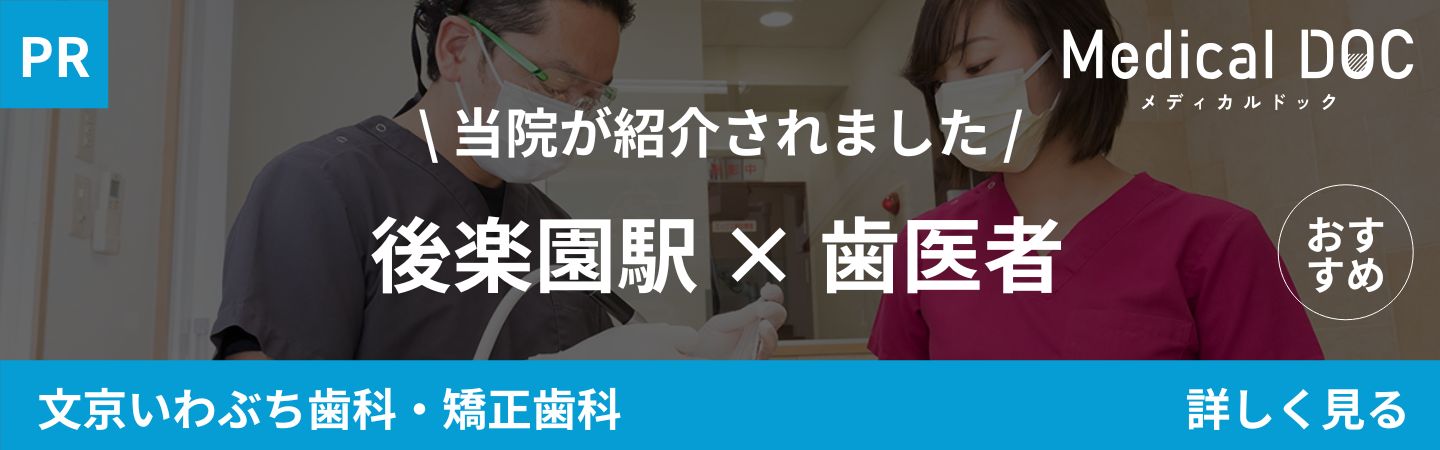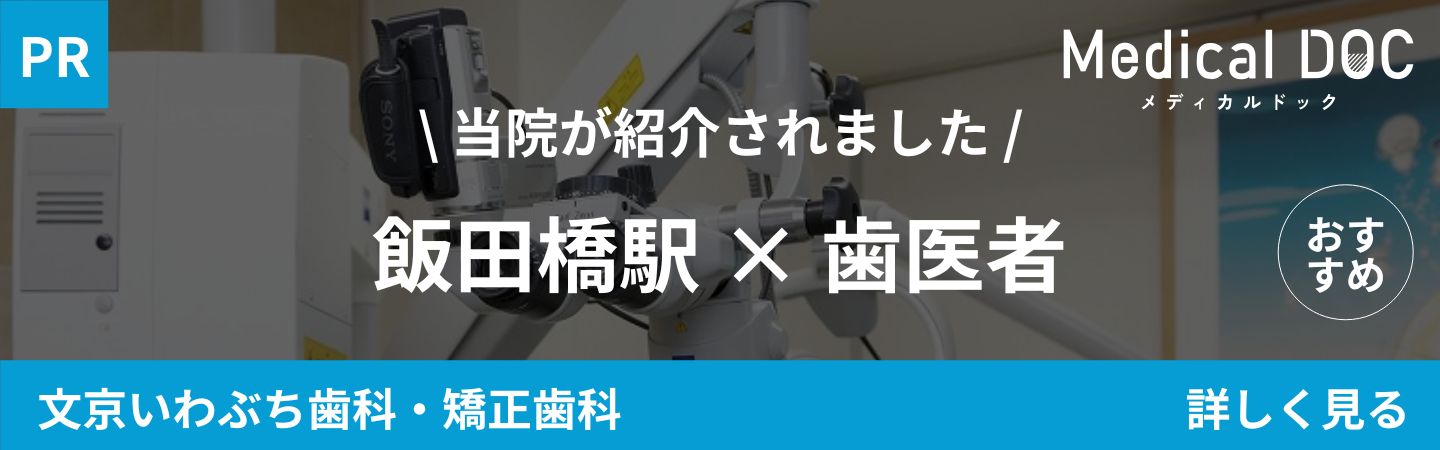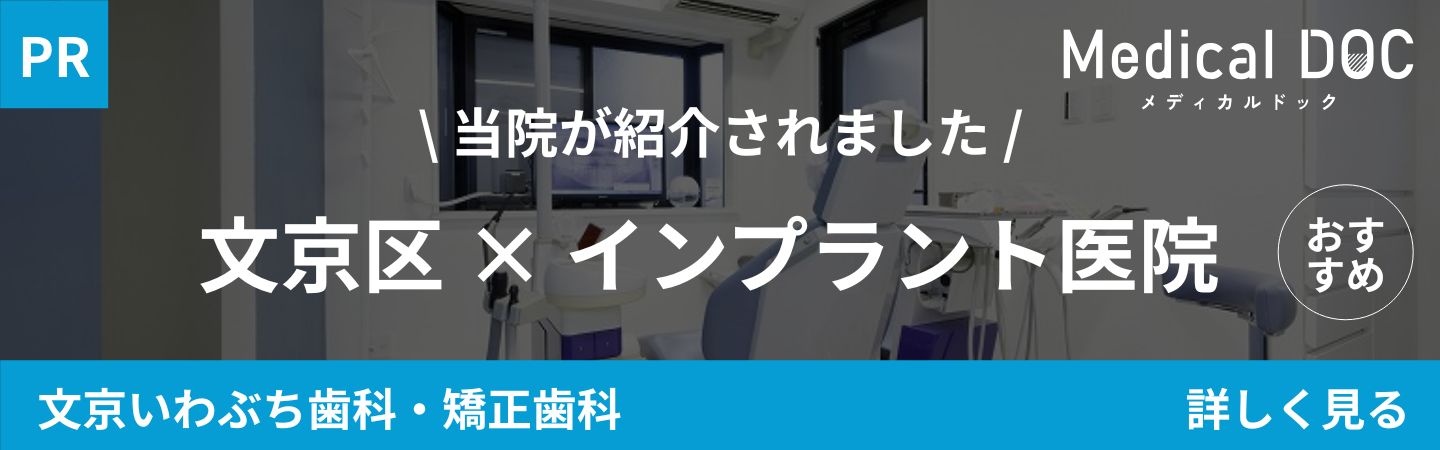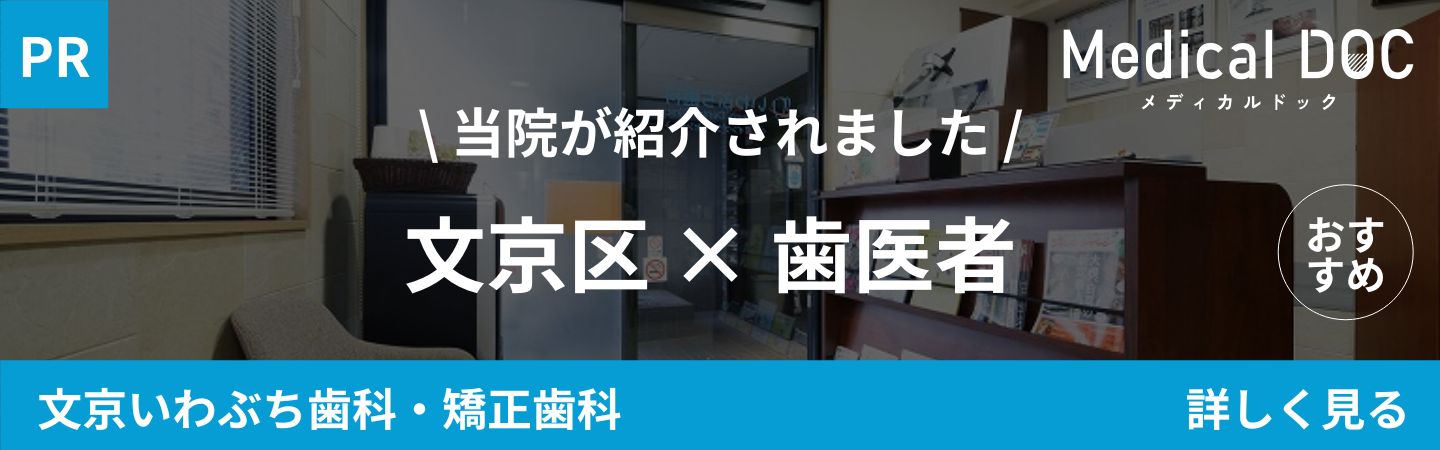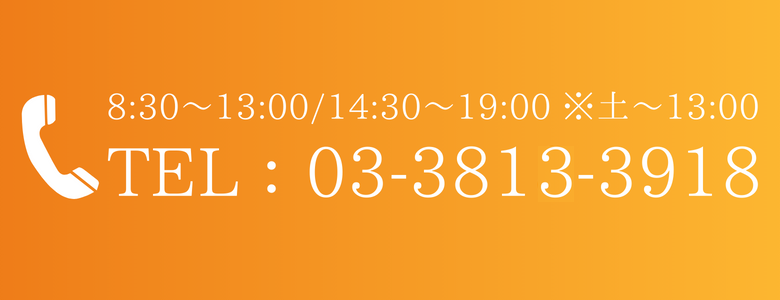子どもの歯医者デビュー、適切な時期と準備方法とは?

文京区後楽園駅・飯田橋駅から徒歩5分の歯医者・矯正歯科「文京いわぶち歯科・矯正歯科」です。
お子さまが2歳に近づき、歯が生えそろってきた頃、「そろそろ歯医者さんに連れて行くべきかな?」と考える保護者の方は多いのではないでしょうか。初めてのことなので、「どんなことをするのだろう」「子どもが嫌がらないかな」といった不安を感じるのは自然なことです。しかし、乳歯の時期からの適切なケアは、お子さまの将来の歯の健康を左右する大切な一歩となります。
この記事では、お子さまの歯医者デビューに最適な時期から、初めての歯科検診で具体的に何をするのか、そして親子で安心して受診するための準備方法までを、分かりやすく丁寧に解説します。この記事を読めば、子どもの歯医者デビューに関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って歯科医院へ足を運べるようになるでしょう。
子どもの歯医者デビュー、最適なタイミングはいつ?
お子さまの歯が生え揃ってきたのを見て、「そろそろ歯医者さんに連れて行くべきなのかな」と考える保護者の方は少なくないでしょう。虫歯予防はもちろん、将来の歯並びにも影響があると言われる乳歯のケアは、いつから始めるのが最適なのでしょうか。具体的にいつ頃連れて行くのがベストなのでしょうか?
目安は「最初の歯が生え始めた頃(生後6ヶ月〜9ヶ月)」
子どもの歯医者デビューに最も適した時期は、生後6ヶ月から9ヶ月頃、つまり最初の歯が生え始めた時期です。多くの場合、赤ちゃんは生後6ヶ月頃に下の前歯から生え始めます。このタイミングで一度歯科医院を受診することには、多くのメリットがあります。
まず、虫歯がないクリーンな状態からプロのケアを始められる点が挙げられます。歯が生えたばかりの時期に歯科医院を訪れることで、初期の段階から適切な歯磨き方法や食生活のアドバイスを受けられます。乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く、虫歯の進行が非常に早いため、早期からの予防が不可欠です。
また、この時期に専門家から指導を受けることで、ご家庭でのケアの質が大きく向上します。保護者の方が、お子さまの歯や口の状態に合わせた正しい仕上げ磨きの方法や、フッ素の利用法などを学ぶことで、日々のセルフケアをより効果的に行えるようになり、将来的な虫歯リスクを大きく低減できるでしょう。
遅くとも1歳半までには受診を検討しよう
生後6ヶ月から9ヶ月の時期を過ぎてしまった場合でも、遅くとも1歳半までには歯科医院を受診することを検討しましょう。この時期には、多くの乳歯が生え揃い始め、上下の歯の噛み合わせの状態を確認できるようになります。
1歳を過ぎると、食事の内容も多様になり、おやつを食べる機会も増えるため、虫歯のリスクが高まります。歯科医院では、生え揃った歯のチェックだけでなく、噛み合わせの状態、歯の汚れ具合、そして虫歯の有無を丁寧に診察してくれます。また、必要に応じてフッ素塗布などの予防処置を受けることも可能です。
1歳半頃までにかかりつけの歯科医院を見つけておくことは、自治体で行われる1歳6ヶ月児健診をスムーズに受けるためにも重要です。また、万が一、歯に関するトラブルが発生した場合でも、日頃からお子さまの口の状態を把握しているかかりつけ医がいれば、より迅速かつ適切な対応を受けられるでしょう。
なぜ早い時期からの受診が大切なの?3つの理由
乳歯の段階から歯科医院に通うことは、お子さまの将来の歯の健康に大きく影響します。ここでは、その大切な理由を3つの観点から掘り下げていきます。
理由1:虫歯の早期発見と予防ができる
乳歯が永久歯に比べて虫歯になりやすいことをご存知でしょうか。乳歯のエナメル質は永久歯よりも薄く、構造も未成熟なため、一度虫歯ができると非常に早く進行してしまいます。そのため、早期に歯科医院を受診し、虫歯がないか定期的にチェックしてもらうことが何よりも重要です。
乳歯の虫歯を放置すると、様々な悪影響が生じます。虫歯菌が口の中に広がり、次に生えてくる永久歯まで虫歯になりやすくなるだけでなく、乳歯が早期に抜けてしまうと、永久歯の生えるスペースが不足し、将来的に歯並びが悪くなる原因にもなりかねません。また、虫歯による痛みで食事がしづらくなり、お子さまの成長にも影響を与える可能性があります。
歯科医院では、ご家庭でのケアだけでは難しい専門的な予防処置を受けられます。例えば、歯質を強くして虫歯菌の活動を抑える「フッ素塗布」や、奥歯の溝を塞いで食べカスが溜まるのを防ぐ「シーラント」などが代表的です。これらのプロのケアを早期から継続的に行うことで、お子さまの歯を虫歯からしっかりと守り、健康な状態を長く維持できます。
理由2:歯医者の雰囲気に慣れることができる
「歯医者さんは怖い場所」というネガティブなイメージは、大人にとっても子どもにとっても避けたいものです。お子さまが初めて歯科医院を訪れる際、虫歯の治療ではなく、痛みや不快感のない定期検診から始めることで、歯科医院に対して良い印象を持つことができます。
健康な状態から通い始めることで、お子さまは歯科医院を「歯をきれいにしてもらう場所」「歯の健康を守る楽しい場所」と認識しやすくなります。定期的に通ううちに、歯科医師や歯科衛生士とのコミュニケーションにも慣れ、器具を見たり、椅子に座ったりすることへの抵抗感も自然と減っていくでしょう。
小さい頃から歯科医院の雰囲気に慣れておくことは、将来的に治療が必要になった場合でも、お子さまがスムーズに診療を受け入れられることにつながります。歯医者に対する恐怖心や嫌悪感を軽減し、生涯にわたるお口の健康習慣を育む上で、早期からの「慣らし」は非常に重要な意味を持つと言えます。
理由3:保護者が正しいケア方法を学べる
お子さまの口の中は、日々の成長とともに常に変化しています。乳歯が生え始める時期から永久歯に生え変わるまで、その時々の発達段階に合わせた適切なケアが必要です。歯科医院に早期から通うことで、保護者の方は専門家から直接、お子さまの口腔状態に合わせた正しいケア方法を学ぶことができます。
例えば、お子さまの歯の生え方や成長段階に応じた仕上げ磨きのコツ、適切な歯ブラシの選び方や歯磨き粉の量、さらには虫歯予防に効果的な食事やおやつの与え方、飲み物に関する注意点など、ご家庭でのセルフケアを充実させるための具体的なアドバイスを得られます。
自己流のケアでは気づけないポイントや、最新の予防に関する知識を専門家から直接学ぶことで、より効果的で確実な虫歯予防を実践できるようになります。歯科医院は、単に治療をする場所ではなく、保護者がお子さまの歯の健康を守るための知識やスキルを習得できる、頼れるパートナーとしての役割も果たしてくれるでしょう。
初めての歯医者さんでは何をするの?当日の流れと診察内容
初めての歯科受診は、親御さんにとってもお子さんにとっても少し緊張するものです。しかし、問診からお口のチェック、予防処置、そしてアドバイスまで、具体的に何をするのかを事前に知っておけば、親子でリラックスして臨めます。このセクションでは、一般的な歯科医院での診察の流れと内容について、一つずつ詳しく解説していきます。
問診・カウンセリング
歯科医院に到着して最初に経験するのが、問診とカウンセリングです。このステップは、お子さんの口腔状態や生活習慣を把握し、最適なアドバイスや治療計画を立てる上で非常に重要になります。保護者の方には、お子さんの既往歴やアレルギーの有無、現在の授乳や食事の状況、おやつの習慣、普段の歯磨きの頻度や方法について記入していただきます。特に、気になることや心配している点があれば、具体的に伝えることで、よりお子さんに合ったケアの提案を受けることができます。
問診票の情報をもとに、歯科医師や歯科衛生士が保護者の方からさらに詳しくお話を聞きます。この時間は、お子さんの歯の健康を守るための大切な情報交換の場となりますので、疑問に思うことや不安なことがあれば、遠慮なく質問してください。この対話を通じて、一人ひとりのお子さんに寄り添ったアドバイスや処置方針が決定されていきます。
お口の中のチェック(歯・歯茎・噛み合わせなど)
問診の次に、お子さんのお口の中を実際に診ていく「お口のチェック」が行われます。小さなお子さんが怖がらないよう、多くの歯科医院では、保護者の方の膝の上にお子さんを抱っこする形で診察を進めます。これにより、お子さんは安心して、保護者の方も診察の様子を間近で見ることができます。
歯科医師は、専用のミラーなどを使って、お子さんの歯の本数や生え方、虫歯の有無、歯茎の状態、そして噛み合わせなどを丁寧に確認します。この時、お子さんが口を開けている間に「バイキンさんがいないか見てみるね」「歯を数えてみようね」といった優しい声かけや、おもちゃを使ったりして、できるだけ恐怖心を与えないように配慮されます。何をされるか分からないという不安を払拭し、お子さん自身も「大丈夫だ」と感じられるような工夫が凝らされています。
虫歯予防のための処置(フッ素塗布など)
お口のチェックで問題がなければ、虫歯予防のための処置が行われることがあります。代表的なものとして「フッ素塗布」があります。フッ素は歯の表面のエナメル質を強くし、虫歯菌が酸を作り出すのを抑制する効果があります。塗布は、歯にフッ素入りの薬剤を塗るだけの簡単な処置で、痛みは全くなく、短時間で終わります。お子さんへの負担が少ないため、歯科医院での定期的なフッ素塗布は、効果的な虫歯予防として広く推奨されています。
また、奥歯の溝が深く、そこに食べかすが詰まりやすいお子さんには、「シーラント」という予防法が提案されることもあります。シーラントは、奥歯の溝を歯科用のプラスチックで埋めて、食べかすやプラークが溜まるのを防ぎ、虫歯のリスクを低減する処置です。これらの予防処置は、お子さんの将来の歯の健康を守るために非常に有効な手段と言えるでしょう。
歯磨き指導などのアドバイス
診察の最後には、保護者の方を対象とした歯磨き指導や、日常生活での虫歯予防に関するアドバイスが行われます。お子さんのお口の状態や発達段階、そして歯磨きの習熟度に合わせて、歯科衛生士が仕上げ磨きの具体的なコツを教えてくれます。
例えば、歯ブラシの正しい当て方や動かし方、力の入れ具合、磨き残しが多い場所などを、実際に模型を使ったり、保護者の方の歯ブラシを使ったりしながら実演してくれます。また、甘いものの与え方や食事のタイミング、飲み物の選び方など、日々の生活の中で実践できる虫歯予防のアドバイスも聞くことができます。これらの専門的な指導やアドバイスは、保護者の方の自己流のケアでは気づけないポイントが多く、家庭でのケアの質を大きく向上させることにつながります。
歯医者デビューを成功させるための準備と心構え
子どもの歯医者デビューを成功させるためには、事前の準備と当日の心構えが鍵となります。ここでは、受診前と受診当日に分けて、親御さんがお子さんと一緒に安心して歯科医院に足を運ぶための具体的なアクションプランをご紹介します。この情報を参考に、ぜひ実践的なノウハウを取り入れてみてください。
【受診前】お家でできる3つの準備
これからご紹介する3つの簡単な準備をすることで、お子さんの歯医者さんへの不安を和らげ、スムーズな受診につなげることができます。
歯医者をテーマにした絵本や動画でイメージ作り
歯医者デビュー前の準備として、歯医者さんをテーマにした絵本や動画を活用することが有効です。例えば、キャラクターが楽しそうに歯のチェックを受けるストーリーの絵本を選んだり、歯科医院の様子が明るく描かれているアニメーションを見せたりするのも良いでしょう。
視覚を通して「歯医者さんは怖くない場所」「歯をピカピカにしてもらえる場所」というポジティブなイメージを事前にインプットすることで、お子さんが抱くかもしれない抵抗感や不安を和らげる効果が期待できます。絵本や動画を一緒に楽しみながら、自然な形で歯医者さんへの親しみを持たせてあげましょう。
「痛い」「怖い」など不安を煽る言葉は避ける
お子さんを歯医者さんに連れて行く際、親御さんが使う言葉には十分な配慮が必要です。「痛くないから大丈夫だよ」「怖くないよ」といった、一見安心させようとする言葉も、かえって「もしかしたら痛いことや怖いことをされるのかもしれない」と、お子さんに余計な警戒心を与えてしまうことがあります。
代わりに、「歯をピカピカにしてもらおうね」「バイキンさんがいないか見てもらおうね」といった、具体的でポジティブな言葉を選ぶように心がけてください。歯医者さんがお子さんの健康をサポートしてくれる存在であることを伝え、前向きな気持ちで受診に臨めるように誘導してあげることが大切です。
歯医者さんごっこで遊びながら慣れる
お子さんが歯医者さんに慣れるための楽しい事前準備として、「歯医者さんごっこ」を取り入れてみましょう。親御さんが「歯医者さん」役になり、お子さんが「患者さん」役でお口を大きく「あーん」と開ける練習をします。小さな手鏡やスプーンを使って、歯の数を数えたり、「むし歯さん、いないかな?」と声をかけながら歯を見たりするのも良いでしょう。
また、お子さんが普段使っている歯ブラシを使って、歯磨きの様子を再現するのも効果的です。遊びを通して診察の流れを疑似体験することで、当日の緊張感を和らげ、スムーズに歯科医院の雰囲気に溶け込めるようになることが期待できます。
【受診当日】保護者が気をつけたいポイント
歯医者さんへの受診当日、親御さんのちょっとした配慮が、お子さんの気持ちを大きく左右します。これからご紹介する2つのポイントを押さえて、お子さんにとって良い体験となるように心がけてください。
機嫌の良い午前中に予約する
お子さんの歯医者デビューを成功させるためには、予約時間帯の選び方も重要なポイントです。お子さんの機嫌が良く、体力も十分にある午前中、特に朝食後や午前のお昼寝の前に予約を入れることをおすすめします。
午後の遅い時間帯や夕方になると、お子さんは疲れが出てきてぐずりやすくなる傾向があります。無理に連れて行くと、歯医者さんに対するネガティブな印象を与えてしまう可能性も考えられます。お子さんの生活リズムを考慮し、最も落ち着いて受診できる時間帯を選ぶことで、スムーズに診察を進めることができるでしょう。
終わった後はたくさん褒めてあげる
診察が終わった後は、お子さんをたくさん褒めてあげることが大切です。ただ漠然と「よく頑張ったね」と言うだけでなく、「大きくお口を開けられて偉かったね」「先生のお話をじっと聞いていられたね」など、具体的にできた行動を褒めるのが効果的です。
親御さんからの肯定的な言葉は、お子さん自身に達成感を与え、「歯医者さんは頑張れば褒めてもらえる場所」という良い記憶として残ります。このポジティブな経験が、次回の定期検診や将来の歯科受診への意欲につながるでしょう。
信頼できる小児歯科の選び方4つのポイント
子どもの歯医者デビューは、親御さんにとっても大きな一歩ですよね。初めての場所で、慣れないことをされるお子さんが不安にならないよう、そして親御さんも安心して任せられる「かかりつけ医」を見つけることが何よりも重要です。特に、子どものお口の診察には、大人とは異なる専門知識と経験が求められます。そのため、0歳から中学生くらいまでを対象とする小児歯科を選ぶことをおすすめします。
小児歯科では、子どもの発達段階に応じた治療や予防が行われるだけでなく、歯医者嫌いにならないための様々な工夫が凝らされています。これから、信頼できる小児歯科を選ぶための具体的な4つのポイントについて詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
ポイント1:子どもの対応に慣れているか
小児歯科を選ぶ上で最も大切なポイントの一つは、そこで働くスタッフ全員が子どもの対応に慣れているかどうかです。歯科医師はもちろんのこと、歯科衛生士、そして受付スタッフまで、子どもが不安なく過ごせるような配慮が行き届いているかを確認しましょう。
例えば、お子さんが泣き出してしまったり、なかなかお口を開けてくれなかったりしたときに、急かしたり叱ったりするのではなく、優しく声をかけ、遊びを取り入れながら臨機応変に対応してくれる姿勢があるかが重要です。こうしたスタッフの対応は、お子さんが歯医者に対して抱くイメージを大きく左右します。
実際に受診する前に、クリニックのウェブサイトで小児歯科に力を入れている旨が記載されているか、あるいは電話で問い合わせた際に、子どもの患者に対する対応について質問してみるのも良いでしょう。待合室で他のお子さんがどのように対応されているかを観察することも、見極めるためのヒントになります。
ポイント2:説明が丁寧で分かりやすいか
親御さんにとって、子どものお口の状態や今後の治療・予防方針について、納得のいく説明を受けられるかどうかは非常に重要です。専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれる歯科医院を選びましょう。
例えば、「お子さんの虫歯の進行状況はどうなっているのか」「なぜこの治療が必要なのか」「フッ素塗布はどんな効果があるのか」といった疑問に対し、時間をかけて丁寧に答えてくれる歯科医師こそ、長期的に信頼できるパートナーとなりえます。治療の選択肢が複数ある場合には、それぞれのメリット・デメリットを詳しく説明し、親御さんの意見を尊重してくれる姿勢があるかどうかも確認したいポイントです。
質問しやすい雰囲気であるか、親御さんの不安や疑問を真摯に受け止めてくれるかなど、コミュニケーションの取り方も重要な判断基準となります。
ポイント3:子どもがリラックスできる環境か
子どもが歯医者に対して「怖い場所」という印象を持たないようにするためには、院内の環境も非常に大切です。子どもがリラックスして過ごせるような工夫がされている歯科医院を選びましょう。
具体的には、待合室に絵本やおもちゃが置かれたキッズスペースが用意されているか、あるいは診察台にアニメが流れるモニターが設置されているかなどが挙げられます。このような工夫は、子どもの緊張をほぐし、待ち時間や診察時間を少しでも楽しく過ごせるようにするためのものです。
また、院内全体が明るく清潔であるか、子ども向けのカラフルな装飾が施されているかなども、子どもが「楽しい場所」と感じるための重要な要素です。実際に足を運んでみて、お子さんが快適に過ごせそうか、親御さん自身の目で確認することをおすすめします。
ポイント4:通いやすい場所にあるか
どんなに良い歯科医院でも、通い続けることができなければ意味がありません。定期的な検診や、万が一の急なトラブルに対応するためには、自宅や保育園、職場などからアクセスしやすい場所にあるかどうかも重要なポイントです。
公共交通機関でのアクセスが良いか、専用の駐車場が完備されているか、あるいは自転車で通える距離にあるかなど、ご自身のライフスタイルに合った立地条件を考慮しましょう。予約の取りやすさや診療時間なども、継続して通院するためには欠かせない要素です。
「少し遠くても、良い歯医者を選びたい」という気持ちもわかりますが、無理なく通える範囲で、お子さんの将来の歯の健康を任せられるかかりつけ医を見つけることが、結果として長く良い関係を築く鍵となります。
子どもの歯医者デビューに関するQ&A
ここでは、子どもの歯医者デビューに関して、保護者の皆さんがよく抱かれる疑問についてお答えします。具体的な質問と回答を通して、最後の不安や疑問を解消していきましょう。
Q. 診察中に泣いてしまっても大丈夫?
お子さんが診察中に泣いてしまっても、まったく心配ありません。お子さんが泣くのは当たり前のことですし、小児歯科のスタッフは、お子さんの対応や、泣いてしまうお子さんへの適切な接し方に慣れています。無理に押さえつけたりせず、お子さんの気持ちに寄り添いながら、診察を進めてくれますのでご安心ください。
保護者の皆さんが焦ったり、申し訳ないと感じたりする必要は一切ありません。むしろ、冷静にお子さんを見守り、必要に応じて優しく声かけをしてあげることが大切です。歯科医院側も、お子さんがリラックスできるよう最大限配慮してくれますので、安心して任せましょう。
Q. 費用はどのくらい?保険は使える?
お子さんの歯科診療は、虫歯の治療はもちろん、定期検診やフッ素塗布といった虫歯予防のための処置も、基本的に健康保険が適用されますのでご安心ください。
さらに、多くの自治体では「子ども医療費助成制度」が設けられており、乳幼児から中学生くらいまでのお子さんの医療費(歯科診療含む)が、窓口で無料になる、あるいは自己負担が数百円程度で済む場合があります。お住まいの自治体の制度を確認してみると良いでしょう。ただし、自由診療となる特殊な矯正治療や、歯科医院独自の予防プログラムなど、一部保険適用外の処置もありますので、気になる場合は事前に歯科医院に確認すると安心です。
Q. 定期検診の頻度はどのくらいですか?
子どもの定期検診の頻度は、一般的に「3ヶ月から6ヶ月に一度」が目安とされています。お子さんの口腔内の状況は成長とともに変化しやすいため、このくらいの頻度で定期的にチェックを受けることが推奨されています。
ただし、この頻度はあくまで一般的なものであり、お子さん一人ひとりの虫歯のリスク(歯並びの状態、食生活、歯磨きの習熟度など)によって最適な頻度は異なります。例えば、虫歯になりやすいお子さんや、歯磨きがまだ難しいお子さんの場合は、もう少し短い間隔での受診をすすめられることもあります。かかりつけの歯科医師が、お子さんの状態に合わせて最適な定期検診の頻度を提案してくれますので、その指示に従うことが最も重要です。
Q. 乳歯の虫歯は放っておいても大丈夫?
「乳歯の虫歯はいずれ永久歯に生え変わるから、放っておいても大丈夫」と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、これは大きな誤解です。乳歯の虫歯を放置することは、お子さんの将来の口腔環境にとって非常に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
まず、乳歯の虫歯が進行すると、その下にある永久歯が作られる部分にまで影響が及び、生えてくる永久歯の質が悪くなったり、変色したりすることがあります。また、痛みがあるために食事が偏り、顎の適切な発達を妨げてしまうことも考えられます。さらに、乳歯が早期に抜けてしまうと、永久歯が生えてくるスペースが確保できなくなり、歯並びが乱れる原因にもなります。
乳歯は、永久歯が生えてくるまでの間、噛むことや発音、そして永久歯のガイド役として非常に重要な役割を担っています。乳歯の健康は、お子さんの口腔全体の土台となるため、虫歯を見つけたら放置せずに、必ず歯科医院で適切な治療を受けるようにしましょう。
まとめ:親子で始める歯の健康づくり
この記事では、お子さまの歯医者デビューについて、最適な時期から具体的な準備、そして信頼できる歯科医院の選び方までを詳しくご紹介しました。
乳歯は永久歯の健康な成長のための大切な土台です。生後6ヶ月から9ヶ月頃、または遅くとも1歳半までには一度歯科医院を受診し、虫歯がない状態から専門的なケアを始めることが、お子さまの将来の口腔環境を守る上で非常に重要です。
初めての歯医者さんは、お子さまにとっても保護者の方にとっても少し緊張するかもしれません。しかし、歯医者さんをテーマにした絵本を読んだり、ご家庭で歯医者さんごっこをしたりするなど、事前の準備をしっかり行うことで、お子さまの不安を和らげることができます。また、歯科医院では「泣いてしまっても大丈夫」という温かい目で、お子さまが少しずつ雰囲気に慣れていけるように配慮してくれますので、安心して受診してください。
そして、お子さまの成長に合わせて、適切なアドバイスをくれる「かかりつけの歯科医院」を見つけることが、長期的な歯の健康につながります。説明が丁寧で、子どもへの対応に慣れていて、通いやすい場所にある歯科医院を選ぶことが大切です。
歯医者さんは、決して怖い場所ではありません。お子さまの成長に合わせた適切なケアの方法を教えてくれる、親子にとって心強いパートナーです。ぜひ、この機会にお子さまとの歯の健康づくりを始めてみませんか。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
日本歯科大学卒業後、医療法人社団学而会 永田歯科医院勤務、医療法人社団弘進会 宮田歯科医院に勤務し、
医療法人社団ビーズメディカル いわぶち歯科開業
【所属】
・日本口腔インプラント学会 専門医
・日本外傷歯学会 認定医
・厚生労働省認定臨床研修指導歯科医
・文京区立金富小学校学校歯科医
【略歴】
・日本歯科大学 卒業
・医療法人社団学而会 永田歯科医院 勤務
・医療法人社団弘進会 宮田歯科医院 勤務
・医療法人社団 ビーズメディカルいわぶち歯科 開業
文京区後楽園駅・飯田橋駅から徒歩5分の歯医者
『文京いわぶち歯科・矯正歯科』
住所:東京都文京区後楽2丁目19−14 グローリアス3 1F
TEL:03-3813-3918