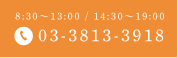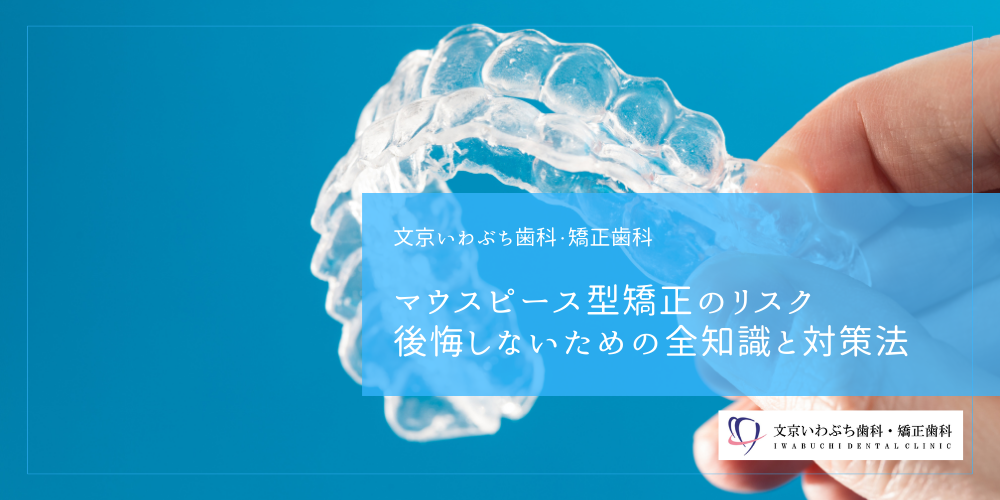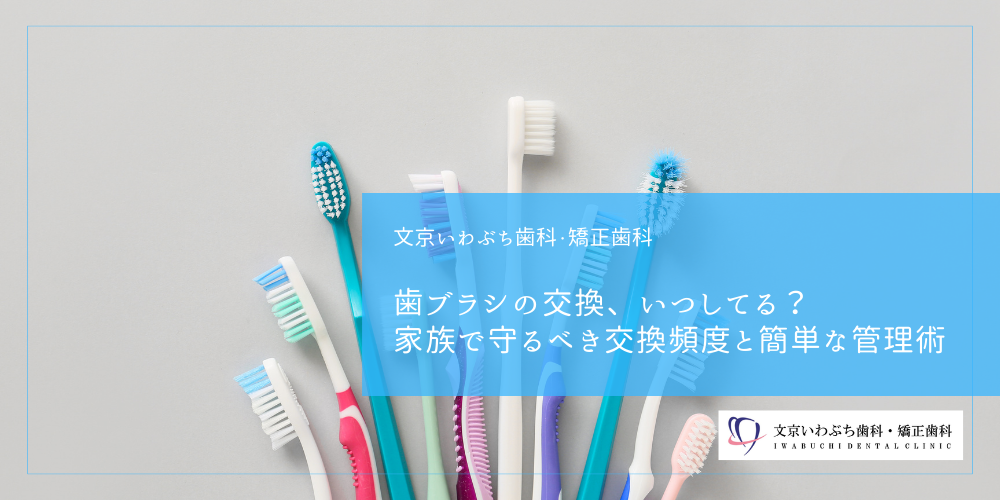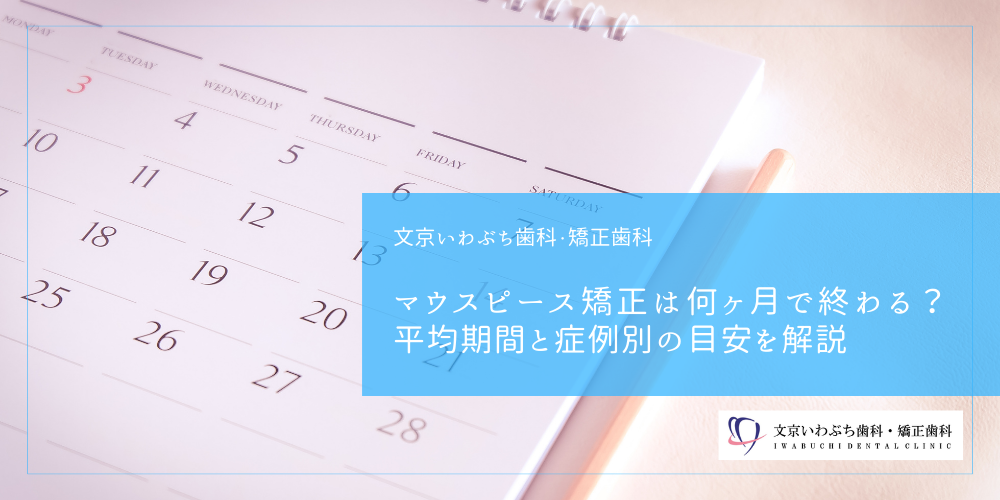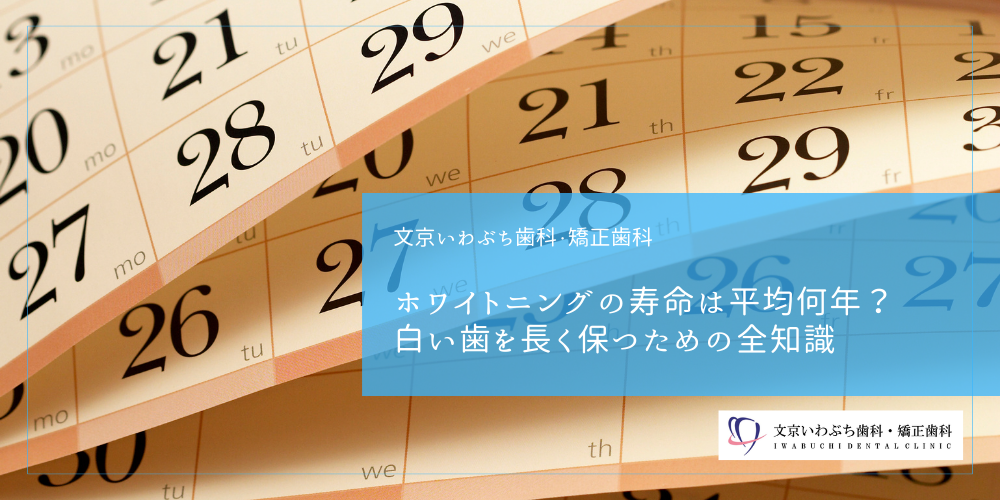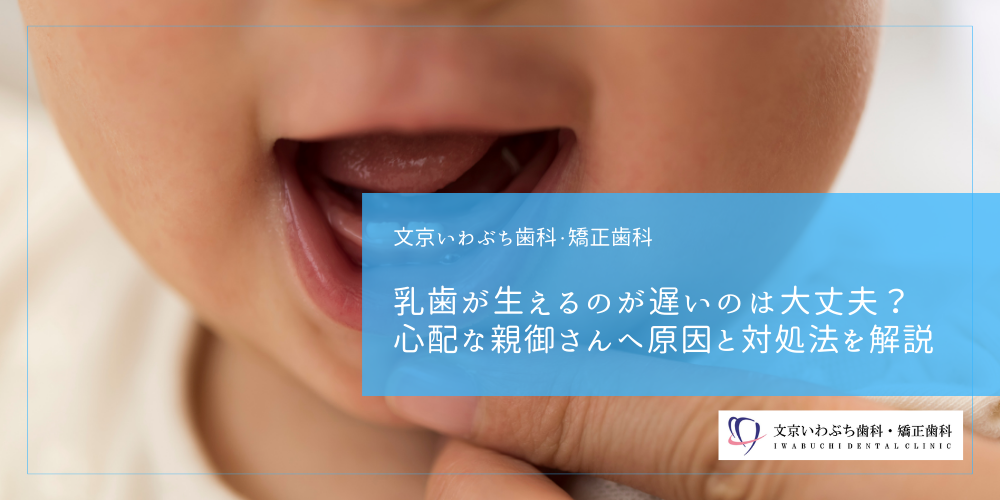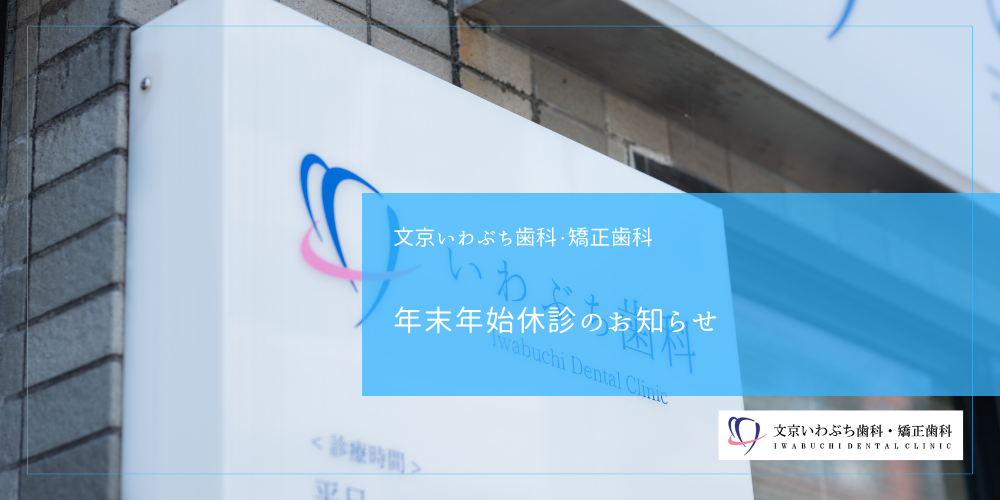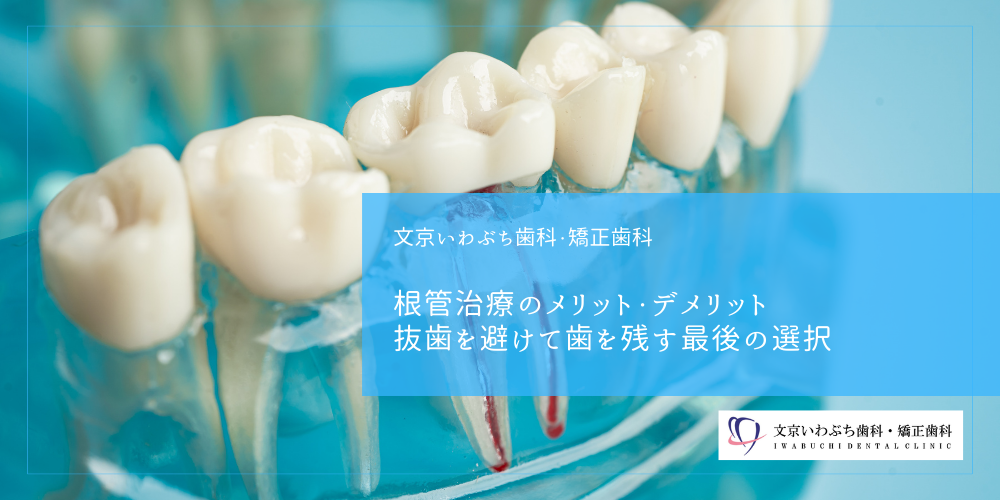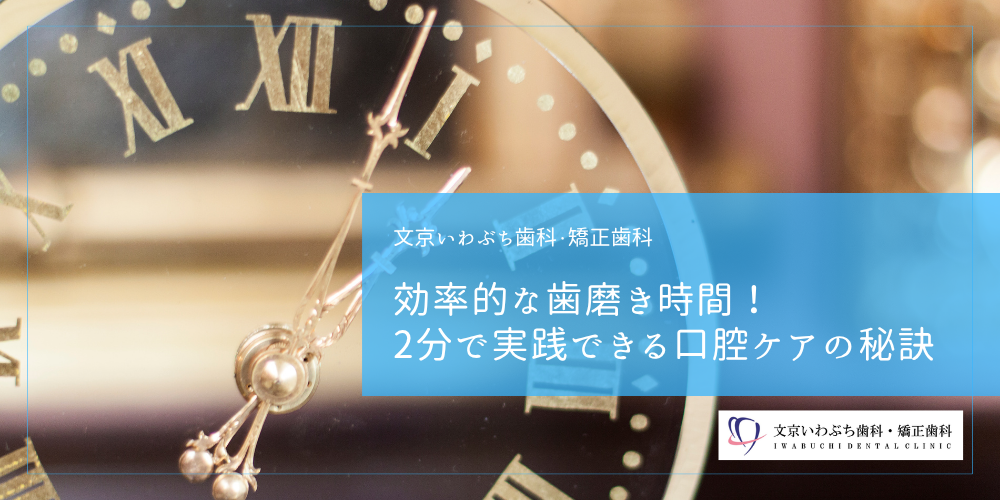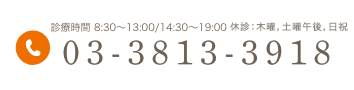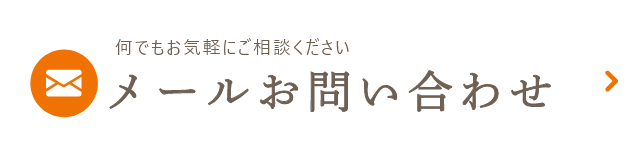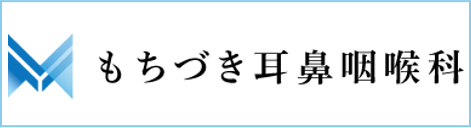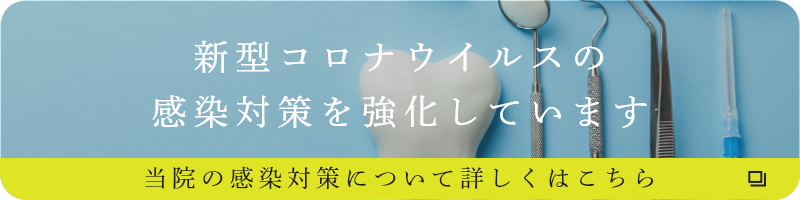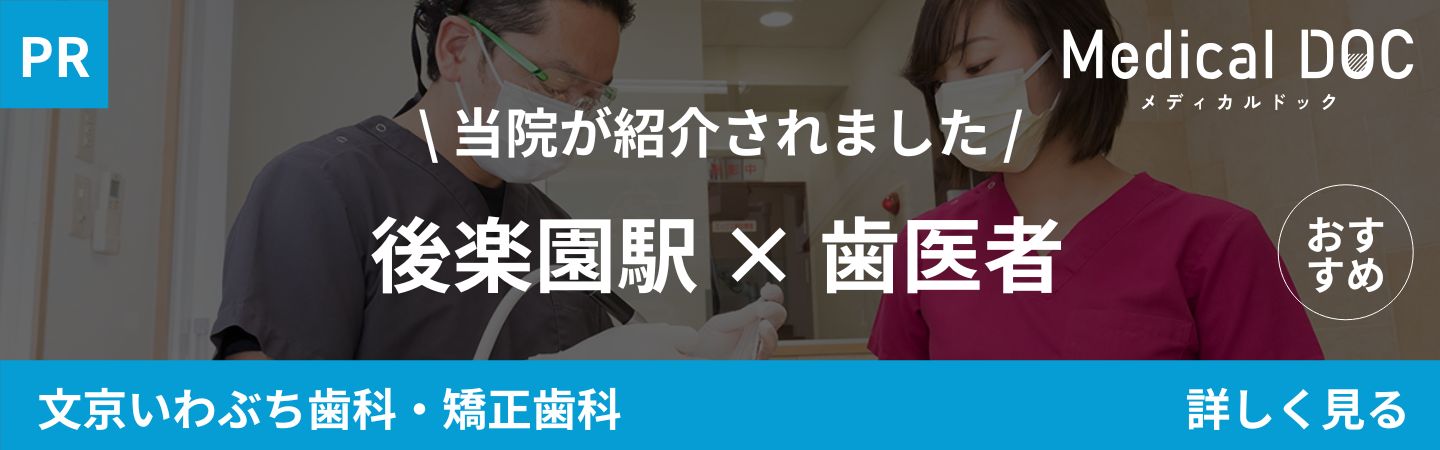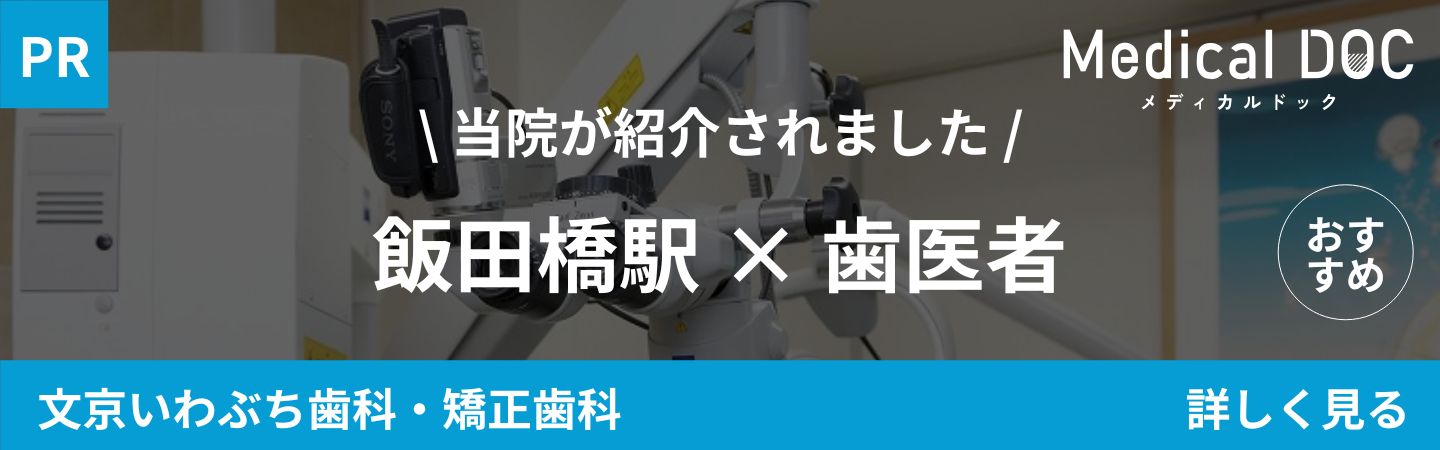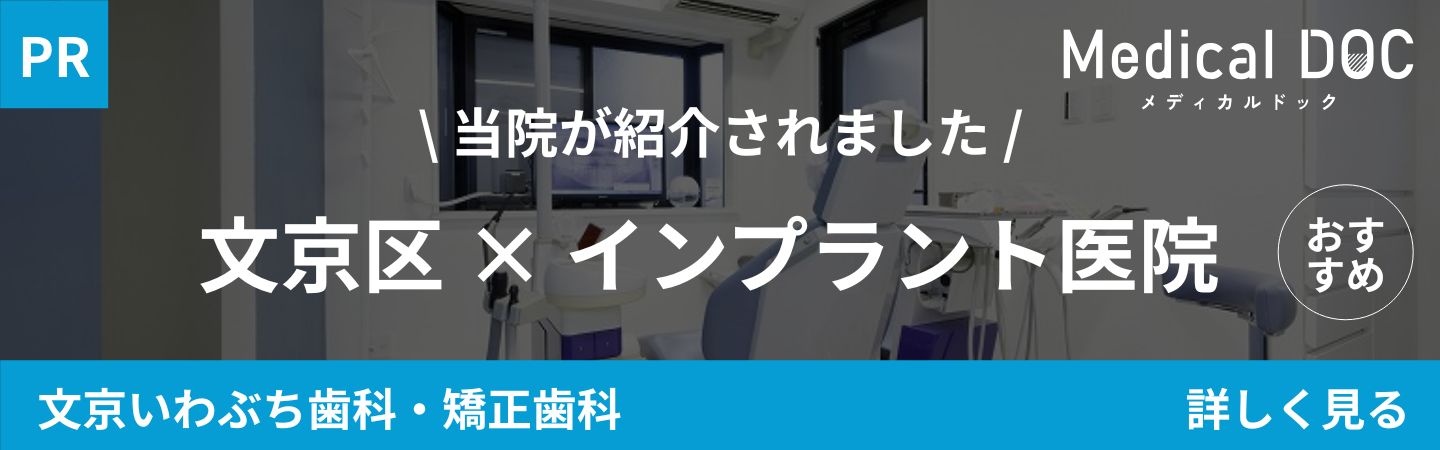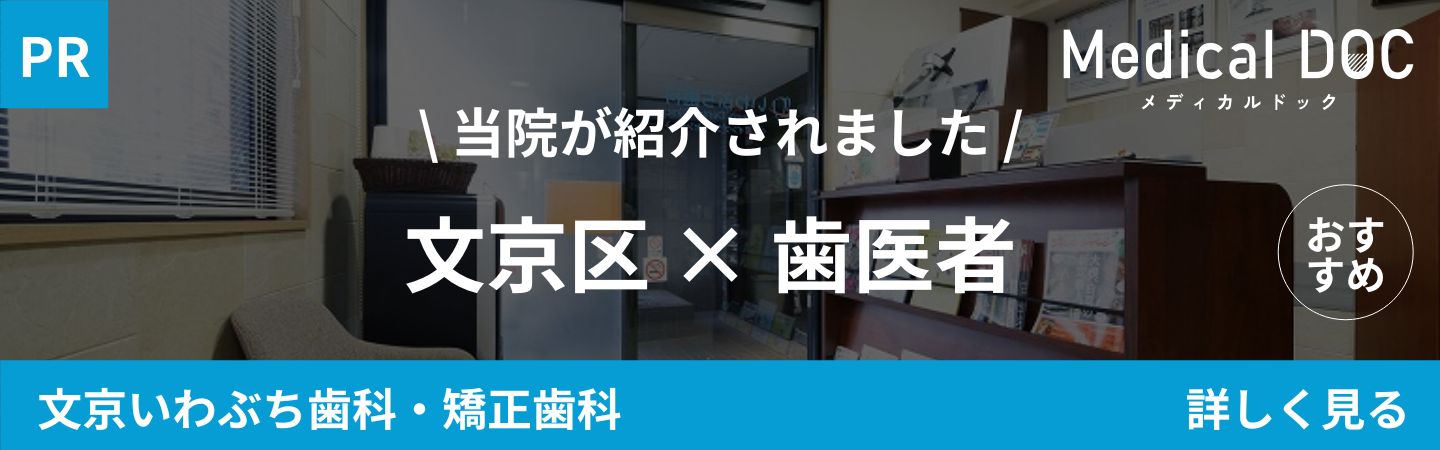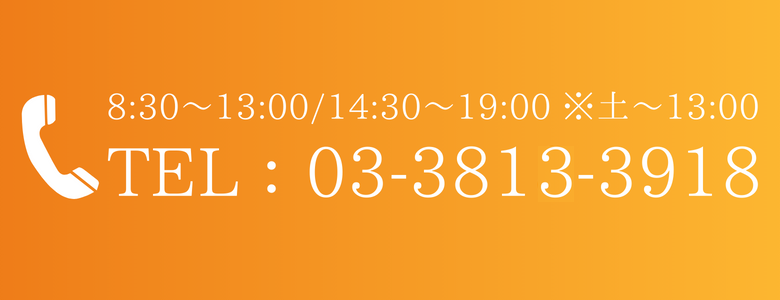歯肉炎悪化を防ぐ!正しい歯磨き方法と日常生活での注意点
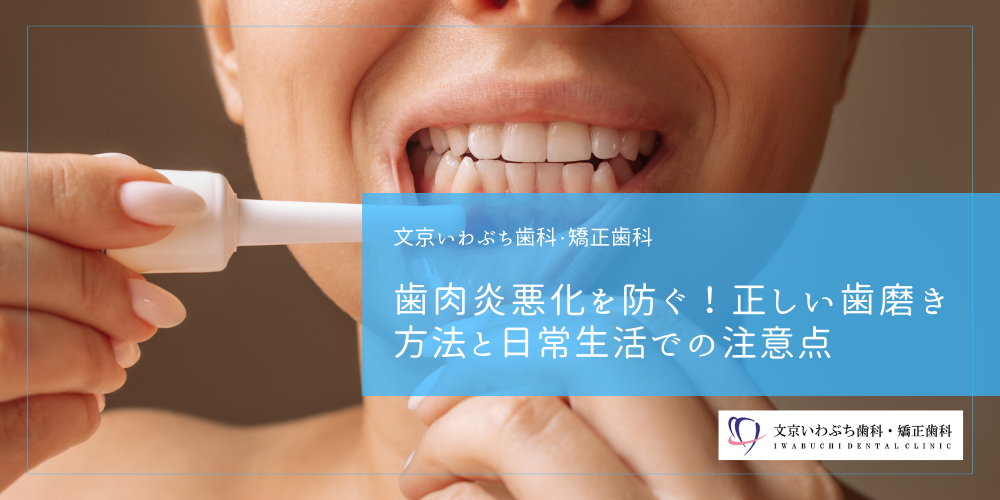
文京区後楽園駅・飯田橋駅から徒歩5分の歯医者・矯正歯科「文京いわぶち歯科・矯正歯科」です。
歯磨き中に歯ぐきから血が出たり、最近、歯ぐきが腫れているような気がしたりすることはありませんか。もしかしたら、それは歯肉炎のサインかもしれません。歯肉炎は多くの方が経験する口腔トラブルの一つですが、「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、より深刻な歯周病へと進行してしまうリスクがあります。
この記事では、歯肉炎の初期症状に気づいた方が、ご自身の状態をセルフチェックし、その原因を深く理解できるよう解説します。歯肉炎を放置した場合の危険性から、ご自宅で実践できる正しいセルフケア方法、さらには食生活や生活習慣の見直しによる予防策、そして歯科医院を受診するべきタイミングまで、歯肉炎に関するあらゆる疑問にお答えします。この記事を読み終える頃には、ご自身の口腔ケアに対する不安が解消され、健康な歯ぐきを取り戻すための具体的な一歩を踏み出せるはずです。
もしかして歯肉炎?気になるサインをセルフチェック
「もしかして歯肉炎かな」と感じたとき、まず確認してほしいのがご自身の歯ぐきの状態です。歯肉炎は自覚症状が少ないこともありますが、注意深く観察するといくつかのサインが見られます。
具体的なサインとしては、まず「歯ぐきが赤く腫れている」状態が挙げられます。健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっていますが、炎症が起きると赤みを帯び、ぷっくりと腫れたように見えます。次に、最も気づきやすいサインの一つが「歯磨きをすると血が出る」ことです。軽いブラッシングでも出血するようであれば、歯ぐきに炎症が起きている可能性が高いでしょう。
また、「歯ぐきがむずがゆい」と感じることもあります。これは炎症によって引き起こされる不快感であり、歯肉炎の初期段階で見られることがあります。これらの症状は、歯と歯ぐきの境目に溜まった細菌の塊(プラーク)によって引き起こされる炎症によるものです。一つでも心当たりのある場合は、歯肉炎のサインかもしれません。ご自身の歯ぐきの状態を客観的にチェックしてみましょう。
歯肉炎の主な原因は歯垢(プラーク)
歯ブラシ時に出血したり、歯ぐきが腫れたりする歯肉炎の根本的な原因は、お口の中に潜む歯垢(プラーク)です。歯垢とは、食べカスや唾液の成分が混じり合って歯の表面に付着する、白くネバネバした細菌の塊のことを指します。この歯垢が歯と歯ぐきの境目に溜まり続けると、その中に含まれる細菌が歯ぐきに炎症を引き起こし、歯肉炎を発症してしまうのです。
歯肉炎は、この歯垢の蓄積から始まる、歯周病の初期段階と言えます。毎日の食事の後、しっかりと歯垢が除去できていないと、歯ぐきは徐々に赤く腫れ上がり、やがてブラッシングなどのちょっとした刺激で出血するようになります。歯肉炎を改善するためには、まずこの歯垢を徹底的に除去することが何よりも大切になります。
歯垢の中に潜む歯周病菌
先ほど歯肉炎の主な原因が歯垢(プラーク)であることをお伝えしましたが、歯垢がなぜ歯ぐきに炎症を引き起こすのか、そのメカニズムについてもう少し詳しく見ていきましょう。歯垢は単なる食べカスではなく、実は数億もの細菌が複雑に絡み合って形成されたバイオフィルムであり、この中に歯周病菌と呼ばれる細菌が多数潜んでいます。
この歯周病菌は、歯ぐきの細胞にとって毒となる物質を常に放出しています。この毒素が歯ぐきの組織を刺激することで、私たちの体は炎症反応を起こし、歯ぐきが赤く腫れたり、出血しやすくなったりといった歯肉炎の症状が現れるのです。つまり、歯垢を除去することは、歯周病菌が作り出す毒素から歯ぐきを守ることに直結するため、歯肉炎の治療や予防において最も重要なケアと言えます。
毎日の丁寧なブラッシングや歯間ケアで歯垢を徹底的に取り除くことが、歯肉炎を改善し、健康な歯ぐきを維持するための第一歩となります。
歯肉炎のリスクを高めるその他の要因
歯肉炎の最も直接的な原因は歯垢(プラーク)ですが、私たちの体の状態や生活習慣も、歯肉炎の発症や悪化に大きく影響することがあります。例えば、ストレスや疲労が蓄積すると、全身の免疫力が低下し、お口の中の細菌に対する抵抗力も弱まってしまいます。その結果、普段は問題にならない程度の歯垢でも、歯ぐきが炎症を起こしやすくなることがあります。
また、妊娠中の女性の場合、ホルモンバランスの変化によって歯ぐきがデリケートになり、歯肉炎が起こりやすくなることが知られています。その他にも、唾液の分泌量が減少するドライマウスの状態では、唾液の自浄作用が十分に機能せず、細菌が繁殖しやすくなります。特定の薬剤の副作用やビタミン欠乏も、歯ぐきの健康に悪影響を及ぼし、歯肉炎のリスクを高める要因となり得ます。
これらの要因は、歯肉炎を悪化させるだけでなく、治療の妨げになることもあります。そのため、口腔ケアだけでなく、日頃から健康的な生活習慣を心がけ、体全体のバランスを整えることが、歯ぐきの健康を維持するためには非常に大切になります。
歯肉炎を放置するとどうなる?歯周病(歯周炎)への進行リスク
歯肉炎は、歯ぐきの病気の初期段階であり、比較的軽度な症状ですが、「たかが歯肉炎」と軽視して適切なケアを怠ると、より深刻な病気へと進行してしまう危険性があります。歯肉炎が進行すると、最終的には歯を支える骨が溶けてしまう「歯周炎」に悪化し、最悪の場合には歯を失うことにもつながりかねません。
このセクションでは、歯肉炎と歯周炎の具体的な違いを詳しく解説し、なぜ歯肉炎の段階で早期に対策を講じることが重要なのか、そして歯周炎まで進行してしまった場合にどのようなリスクがあるのかについて、掘り下げてご紹介していきます。ご自身の歯ぐきの健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
歯肉炎と歯周炎の違い
歯肉炎と歯周炎はどちらも歯周病の一種ですが、その進行度合いと症状に決定的な違いがあります。歯肉炎は、歯と歯ぐきの境目に蓄積した歯垢(プラーク)に含まれる細菌によって歯ぐきだけに炎症が起こっている状態です。主な症状としては、歯ぐきの腫れや赤み、歯磨き時の出血などが挙げられますが、この段階ではまだ歯を支える顎の骨には影響がなく、適切なケアによって元に戻る可能性があります。
一方、歯周炎は歯肉炎がさらに進行し、炎症が歯ぐきだけでなく、歯を支える顎の骨(歯槽骨)や歯根膜などの組織にまで及んでいる状態を指します。歯周炎になると、歯肉炎で見られた症状に加えて、歯ぐきが下がって歯が長く見える「歯肉の退縮」や、歯周ポケットから「膿」が出る、常に口の中がネバつく「口臭」が気になる、冷たいものがしみる「知覚過敏」、そして最終的には歯を支える骨が溶かされて「歯がグラグラする」といった深刻な症状が現れます。
つまり、歯肉炎が歯ぐきの表面的な炎症であるのに対し、歯周炎は歯を支える土台そのものが破壊され始める、より重篤な状態だと言えます。歯肉炎は自覚症状が少ないこともありますが、これらの違いを理解することで、ご自身の口腔内の状態をより正確に把握し、適切な対応を検討するきっかけになるでしょう。
歯周炎まで進行すると歯を失う可能性も
歯周炎が進行すると、歯を失うという最も深刻な結果を招く可能性があります。歯周炎は、歯ぐきの炎症が歯を支える顎の骨にまで広がり、その骨を徐々に溶かしてしまう病気です。骨が溶けていくと、歯をしっかりと固定していた土台が失われるため、歯がグラグラと揺れ始めます。最初はわずかな動揺でも、病状が進むにつれて動揺が大きくなり、最終的には食事をする際にも痛みを感じるようになり、やがては自然に抜け落ちてしまうことさえあります。
実は、成人の約8割が歯周病に罹患しているか、その予備軍であると言われています。自覚症状がないまま病気が進行しているケースも少なくありません。歯肉炎の段階であれば、適切なケアで症状を改善し、健康な歯ぐきを取り戻すことが十分に可能です。しかし、歯周炎まで進行してしまうと、一度溶けてしまった骨を完全に元に戻すことは非常に難しくなります。
そのため、歯肉炎の段階で病気の進行を食い止めることが、将来にわたってご自身の歯を一本でも多く残すための鍵となります。歯ぐきの異変に気づいたら、「まだ大丈夫だろう」と放置せずに、できるだけ早く対処を始めることが、結果として歯を守ることにつながるのです。
歯肉炎の悪化を防ぐ!今日から始める正しい歯磨き方法
歯肉炎は、日々の適切なケアによって症状の改善が期待できる病気です。特に、その主な原因となる歯垢を毎日きちんと取り除くことが、悪化を防ぐ上で何よりも重要となります。これからご紹介する正しい歯磨き方法を実践することで、多くの方が歯肉炎の改善を実感できるでしょう。
この章では、まず歯ブラシを歯と歯ぐきにどのように当てるべきかという「バス法」の基本、そして歯ブラシだけでは届きにくい部分をケアする「歯間ケア」の重要性について、詳しく解説していきます。
ステップ1:歯ブラシの基本「バス法」
歯肉炎の原因となる歯垢は、特に歯と歯ぐきの境目、いわゆる「歯周ポケット」に溜まりやすいものです。この部分のプラークを効果的に除去するために推奨されているのが、「バス法」と呼ばれる歯磨き方法です。
バス法では、まず歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に対して、45度の角度で軽く当てます。毛先が歯周ポケットに少し入るイメージで当てることがポイントです。その後、力を入れすぎず、小刻みにブラシを振動させるように磨きます。ゴシゴシと強く磨く必要はなく、優しい力で数回動かすことで、歯周ポケット内のプラークをかき出すことができます。この方法を、歯を1本ずつ丁寧に磨くように、全ての歯に実践してみましょう。
ステップ2:歯間ブラシやデンタルフロスで歯と歯の間をケア
実は、通常の歯ブラシだけでは、歯と歯の間に溜まった歯垢の約6割しか除去できないと言われています。残りの歯垢は、歯肉炎や虫歯の原因となるため、歯ブラシでは届かない「歯と歯の間」をケアすることが非常に大切です。
そこで活用したいのが、デンタルフロスと歯間ブラシです。デンタルフロスは、歯と歯の間の狭い隙間や、まだ歯ぐきが下がっていない部分のケアに適しています。フロスを約40cmに切り、両手の中指に巻き付け、親指と人差し指で持って、歯の側面に沿わせるようにゆっくりと挿入し、歯肉溝(歯と歯ぐきの溝)まで入れ、数回上下に動かしてプラークを絡め取ります。
一方、歯間ブラシは、歯ぐきが下がって歯と歯の間に隙間ができた部分や、ブリッジの下などの清掃に有効です。自分の歯間の大きさに合ったサイズの歯間ブラシを選び、無理なく挿入できるものを使用しましょう。誤ったサイズや使い方をすると、歯ぐきや歯を傷つける可能性がありますので、不安な場合は歯科医師や歯科衛生士に相談して、正しい使い方と適切なサイズを教えてもらうことをおすすめします。毎日の歯磨きにこれらの歯間ケアをプラスすることで、歯垢除去効果が格段に高まり、歯肉炎の予防・改善につながります。
セルフケアを補助するアイテムの活用
歯肉炎を改善するためには、毎日の正しい歯磨きと歯間ケアが基本となります。しかし、これらの基本的なセルフケアを補完し、より効果を高めるための市販アイテムも存在します。これらのアイテムは、あくまで日々のブラッシングで取り除ききれないプラークへの対策や、炎症を一時的に和らげるための補助的な役割を果たすものです。
これから、マウスウォッシュや市販薬といったセルフケア補助アイテムについて、それぞれの役割と正しい使い方を具体的にご紹介します。これらを上手に活用することで、より健康な口腔環境を目指しましょう。
マウスウォッシュの役割と選び方
マウスウォッシュは、口の中をリフレッシュさせたり、殺菌成分で口腔内の細菌を減らしたりする効果が期待できますが、歯肉炎の根本的な治療にはならないことを覚えておきましょう。歯ブラシが届きにくい場所の細菌を一時的に減らすことや、歯肉炎による不快感を軽減することには役立ちますが、歯と歯ぐきの間にこびりついたプラーク(歯垢)を物理的に除去する効果はありません。
歯肉炎対策としてマウスウォッシュを選ぶ際は、殺菌成分(CPCやIPMPなど)や抗炎症成分(グリチルリチン酸ジカリウムなど)が配合されているものを選ぶと良いでしょう。使用するタイミングは、歯磨き後の清潔な状態で行うのが効果的です。ただし、アルコール含有量の多い製品は、口の中を乾燥させてしまう場合があるため、ドライマウスの症状がある方や刺激に敏感な方はノンアルコールタイプを選ぶことをおすすめします。
マウスウォッシュは、毎日のブラッシングやフロス、歯間ブラシと組み合わせて使うことで、より効果的な口腔ケアが期待できます。しかし、マウスウォッシュだけで歯肉炎が治るわけではないため、過信せずに、あくまで補助的なアイテムとして活用してください。
歯ぐきの腫れや痛みに使える市販薬
歯肉炎による歯ぐきの腫れや痛みが強く、日常生活に支障が出ている場合には、市販薬を活用して一時的に症状を和らげることができます。ドラッグストアなどでは、歯ぐきに直接塗るタイプの抗炎症作用のある塗り薬や、内服するタイプの痛み止めが販売されています。
歯ぐきに塗るタイプの薬は、患部に直接作用し、炎症を抑えたり、痛みを和らげたりする効果が期待できます。また、痛みがひどい場合は、一般的に用いられるアセトアミノフェンやイブプロフェンなどの市販の痛み止めを内服することも可能です。しかし、これらの市販薬はあくまで応急処置であり、症状を一時的に抑えるためのものです。
市販薬で症状が改善しない場合や、数日使用しても効果が見られない場合は、すぐに歯科医院を受診してください。また、持病がある方や服用中の薬がある方は、市販薬を使用する前に必ず歯科医師や薬剤師に相談し、指示に従うようにしましょう。
歯磨き以外の日常生活でできる歯肉炎対策
歯肉炎対策は、歯ブラシによる日々の丁寧なブラッシングだけでは十分ではありません。実は、口腔内の健康は体全体の健康状態と密接に結びついており、日々の食事や生活習慣が歯ぐきの健康に大きく影響を及ぼします。歯周病菌と戦う体の免疫力を高めること、そして歯ぐきに良い栄養を供給することは、歯磨きという「外からのケア」と同じくらい、あるいはそれ以上に重要な「内からのケア」と言えるでしょう。
このセクションでは、なぜ食生活、適切な生活習慣、そして禁煙が歯ぐきの健康につながるのか、その関連性を詳しく解説していきます。これらの要素を見直すことで、歯肉炎の改善だけでなく、再発予防にも役立ち、より総合的なアプローチで健康な口腔環境を維持できるようになります。
バランスの取れた食事とよく噛む習慣
歯ぐきの健康を維持するためには、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。特に、歯ぐきを構成するコラーゲンの生成を助けるビタミンCは重要です。ビタミンCは、ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜、柑橘類やイチゴなどに豊富に含まれています。また、骨や歯の健康に不可欠なカルシウムやビタミンDも、歯周組織の健康をサポートするために重要です。偏りのない食事を心がけ、これらの栄養素を積極的に摂取することが、健康な歯ぐきを育む基本となります。
さらに、「よく噛む」習慣も歯肉炎対策に非常に効果的です。食事の際にしっかり噛むことで唾液の分泌が促進されますが、唾液には口の中の細菌を洗い流したり、酸を中和したりする自浄作用があります。この自浄作用が高まることで、歯肉炎の原因となるプラークの蓄積を防ぎ、口腔内を清潔に保つ手助けをしてくれるのです。一口あたり30回を目標にするなど、意識的に噛む回数を増やすことをおすすめします。
免疫力を高める生活習慣(睡眠・運動)
歯肉炎は、プラーク内の歯周病菌による感染症ですが、体の免疫力が低下していると、炎症が悪化しやすくなります。免疫力を高めるためには、日々の生活習慣を整えることが非常に重要です。特に、十分な睡眠は体の修復と再生を促し、免疫機能が正常に働くために不可欠です。目安として、一日7時間程度の質の良い睡眠を確保することを目指しましょう。睡眠不足はストレスを増加させ、歯ぐきの状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。
また、適度な運動は血行を促進し、新陳代謝を活発にすることで免疫力向上に貢献します。ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、無理なく続けられる運動を日常生活に取り入れてみてください。運動によってストレスが解消されることも、歯ぐきの健康維持には良い影響を与えます。ストレスは免疫機能の低下に繋がりやすいため、リラックスできる時間を作り、心身ともに健康な状態を保つことが、歯肉炎の予防と改善に繋がります。
禁煙を心がける
喫煙は、歯肉炎を含む歯周病にとって最大の危険因子の一つです。タバコに含まれるニコチンやタールなどの有害物質は、歯ぐきの血流を悪化させ、歯ぐきへの酸素や栄養の供給を妨げます。これにより、歯ぐきの免疫機能が低下し、歯周病菌に対する抵抗力が弱まってしまいます。その結果、歯肉炎が発症しやすくなるだけでなく、一度発症すると治りにくくなるという悪循環に陥る可能性があります。
喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病が進行しやすく、治療効果も現れにくい傾向にあります。もし歯肉炎の症状にお悩みであれば、禁煙を真剣に検討することをおすすめします。禁煙は、歯肉炎の改善だけでなく、全身の健康状態にも非常に良い影響をもたらします。歯ぐきの健康を守るために、ぜひ禁煙にチャレンジしてみてください。禁煙が難しい場合は、医療機関のサポートも活用できます。
セルフケアで改善しない場合は歯科医院へ
これまで、ご自宅でできる歯肉炎のセルフケア方法や、日常生活での注意点についてお伝えしてきました。しかし、ご自身で努力を続けても、なかなか歯肉炎の症状が改善しない場合もあります。そのような時は、「いつまで様子を見ればいいのだろう」「歯医者に行くべきか」と悩まれるかもしれません。
このセクションでは、セルフケアで改善が見られない場合の次のステップとして、歯科医院を受診することの重要性をお話しします。歯科医院は、単に怖い場所や痛い治療を受ける場所ではなく、お口の健康を守るための大切なパートナーです。専門的な視点から、あなたの歯肉炎の根本原因を探り、適切な治療法を提案してくれます。具体的な受診の目安や、歯科医院で受けられる治療について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
歯科医院を受診する目安
ご自身で正しい歯磨きや歯間ケアを1週間から2週間程度続けても、歯ぐきの出血や腫れが改善しない場合は、歯科医院の受診を検討しましょう。セルフケアで改善しない症状には、自己判断では見過ごしてしまうような原因が隠れている可能性があります。
また、歯ぐきの痛みが強く日常生活に支障が出ている場合や、歯がグラグラする感じがする、口臭が以前よりも気になるようになったといった症状がある場合も、早めに歯科医院を受診することをおすすめします。歯肉炎は初期症状が少ないため、自覚症状が現れた時には、すでに歯周炎へ進行している可能性もあります。ご自身の判断で放置せずに、専門家である歯科医師の診断を仰ぐことが、症状の悪化を防ぐためにとても重要です。
歯科医院で行う主な治療法
歯科医院では、歯肉炎の原因となる歯垢や歯石を徹底的に除去し、正しいセルフケアを身につけるための指導が行われます。まず行われるのは、「歯磨き指導(TBI:Tooth Brushing Instruction)」です。これは、患者さん一人ひとりのお口の状態や歯並びに合わせた、効果的な歯磨きの方法を歯科衛生士が丁寧に指導するものです。歯ブラシの選び方から、バス法のような特定の磨き方、そして歯間ブラシやデンタルフロスの使い方まで、実践的に学ぶことができます。
次に、ご自身では取り除くことが難しい、歯と歯ぐきの境目や歯周ポケットに付着した歯垢や歯石を専門の器具を使って除去する「スケーリング」が行われます。歯石は歯垢が石灰化したもので、表面がザラザラしているため、さらに多くの歯垢が付着しやすくなる悪循環を招きます。スケーリングによってこれらを除去することで、歯ぐきの炎症が大きく改善されます。もし歯周炎まで進行している場合は、さらに深い部分の歯石を取り除く「ルートプレーニング」や、外科的な治療が必要になることもあります。
予防のために大切な定期検診
歯肉炎や歯周炎は、自覚症状がないまま進行することが多いため、治療後の良い状態を維持し、再発を防ぐためには「予防」の観点からのアプローチが非常に重要です。その中心となるのが、歯科医院での定期検診です。定期検診では、虫歯や歯周病のチェックだけでなく、歯ぐきの状態や噛み合わせ、舌の状態など、お口全体の健康状態を専門家が総合的に診断します。
特に、定期的なプロフェッショナルクリーニングは、ご自身での歯磨きでは落としきれない微細な歯垢や着色汚れを除去し、お口の中を清潔に保つ上で欠かせません。これにより、歯周病菌が増殖しにくい環境を維持し、歯肉炎の再発を防ぎ、ひいては歯の喪失を予防することができます。一般的には、3ヶ月から6ヶ月に一度の定期検診が推奨されていますが、お口の状態によって適切な間隔は異なりますので、歯科医師と相談して決めるようにしましょう。
まとめ:毎日の正しいケアで健康な歯ぐきを維持しよう
今回は、歯ブラシ時に出血する、歯ぐきが腫れているなどのサインから始まる歯肉炎について、その原因からご自宅でできるセルフケア、そして歯科医院を受診するタイミングまでを詳しく解説いたしました。歯肉炎は、歯垢(プラーク)に潜む歯周病菌が原因で引き起こされる、とても身近な病気です。
しかし、正しい知識と適切なケアを実践すれば、その多くは改善し、さらに深刻な歯周炎への進行を防ぐことができます。日々の歯磨きでは、「バス法」で歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨き、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間のプラークもしっかり除去することが大切です。また、食生活の改善、十分な睡眠、適度な運動といった生活習慣の見直しも、免疫力を高め、歯ぐきの健康を保つ上で非常に重要です。
もし、ご自宅でのセルフケアを1週間から10日程度続けても症状が改善しない場合は、迷わず歯科医院を受診してください。歯科医院では、ご自身では除去できない歯石のクリーニングや、一人ひとりに合った正しい歯磨き方法の指導を受けることができます。何よりも、歯肉炎や歯周炎は自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的な歯科検診とプロフェッショナルによるクリーニングが、健康な歯ぐきを維持し、将来的に歯を失うリスクを減らすための最も確実な方法です。
今日からできる正しいケアを実践し、定期的に歯科医院でのチェックを受けることで、健康な歯ぐきを維持し、生涯にわたってご自身の歯でおいしく食事を楽しめるようにしていきましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
日本歯科大学卒業後、医療法人社団学而会 永田歯科医院勤務、医療法人社団弘進会 宮田歯科医院に勤務し、
医療法人社団ビーズメディカル いわぶち歯科開業
【所属】
・日本口腔インプラント学会 専門医
・日本外傷歯学会 認定医
・厚生労働省認定臨床研修指導歯科医
・文京区立金富小学校学校歯科医
【略歴】
・日本歯科大学 卒業
・医療法人社団学而会 永田歯科医院 勤務
・医療法人社団弘進会 宮田歯科医院 勤務
・医療法人社団 ビーズメディカルいわぶち歯科 開業
文京区後楽園駅・飯田橋駅から徒歩5分の歯医者
『文京いわぶち歯科・矯正歯科』
住所:東京都文京区後楽2丁目19−14 グローリアス3 1F
TEL:03-3813-3918